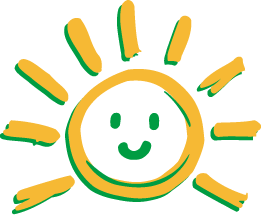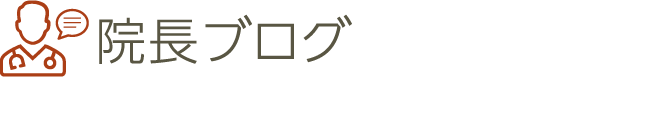
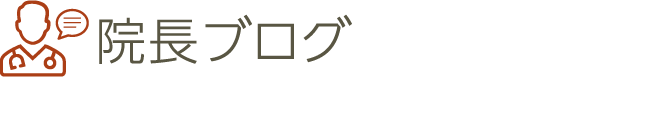
02 訪問診療に思うこと
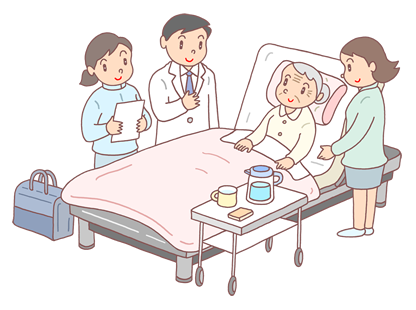 僕は臨床医として30年が過ぎました。
僕は臨床医として30年が過ぎました。
概ね、最初の15年間を大学病院で勤務し、後の15年間を今のクリニックでかかりつけ医として過ごしてきました。どちらでもこの30年間へとへとになりながら、わき目もふらずにひたすら患者さんとの毎日を送ってきました。
大学病院は、特定機能病院に分類され高度な先進医療を提供する病院であり、高度な医療設備の中でいのちぎりぎりの治療にどっぷり浸かっていました。また、臨床の他に教育、研究にも力を注ぎ、この時の研究として、リウマチ・膠原病及び腎臓病を専門に選びました。
その理由の一つとして、膠原病は、皮膚、骨、肺、腎などの臓器を中心にその構成成分であるコラーゲンに障害、炎症が生じる全身性の疾患で、原因に免疫が関与しています。
例として、関節リウマチは、代表的な膠原病です。
僕は、皮膚からあらゆる臓器に及ぶ膠原病は、臓器のひとつの症状から全身症状の診断に至ることができる唯一の疾患であることに興味を覚え専門医になりました。
特に腎臓は、膠原病の合併症として高頻度に障害を認めます。このため、腎臓の障害程度が予後に大きく関わっていて、この重症度により病気の治療法を決定することが多いために、これより腎臓専門医も取得し、腎臓疾患面から治療に当たるようにしてきました。
一方、クリニックでは、風邪、アレルギー、湿疹や高血圧、糖尿病など多岐にわたる病気を診ることが多く、また、患者さんも子供からお年寄りまでと幅広く来院されます。
初めは、診察に戸惑うこともありましたが、膠原病を専門にしているおかげで全身の症状を診るのも慣れているし、何しろ色々な症状を診る診察が楽しく感じました。
また、大学病院時代に埼玉県の大里村という当時、人口が6,500人程度の村で、重度心身障害児施設に5年間非常勤医師として勤務していたことや、その村で毎日、午前の外来が終了し、昼から看護師さんと車で近隣の高齢者を往診していたこともあり、その経験が、子供の診察や往診など今の診療に役立っています。
特に訪問診療は、大学病院の勤務医ではなかなか経験できない診療です。
開院当初は、聴診器、血圧計やたくさんの医薬品を持っていき、できるだけ外来診察と同じような状況で診察ができることに配慮していた気がします。しかし、往診を続けて行くうちに、訪問診療のよいところは、患者さんや家族との距離が近く、のびのびした患者さんとの会話が楽しくできることが診療のひとつであることをより強く感じるようになりました。
この会話のキャッチボールが訪問診療の真骨頂と言ってもいいぐらいです。そのためには、まず、訪問前に患者さんの状態や気持ちを想像しながら、また、このときに診察時の会話を考えながら訪問診療に向かいます。
少し不謹慎かもしれませんが、若い時の20代にデートに行く前の感覚に似ているような気もします。
それだけ、力が入ります。なので、このキャッチボールが上手くできると帰りは清々しい感覚になります。
これもデート後の気持ちと同じです。
そして、訪問時には、自分の言葉で患者さんや家族の心を抱きしめられるように、診察後にありったけの気持ちを伝えます。
これまでに癌や終末期の患者さんの在宅死をたくさん経験しました。
患者さんからそのぎりぎりの在宅の命の発する言葉にこころを揺さぶられる思いもあります。住み慣れた自宅で、家族に見守られながらその人のすべてを出しながら天寿を全うすることを家族とともに受け止めていく。
今まで生きてきたように、怒ったり、笑ったり、泣いたりもあっていいと思います。僕は、医師として痛みや苦しさを取り除くのは当然ですが、きれいにと思うことはないと説明します。すべてを出して天寿に向かい、その人が今まで生きてきた人生を僕自身も肌で感じる。このように“なんでもあり”が在宅の治療の特権であると思います。
訪問診療では、“人の尊厳、はかなさや家族間の愛”を強く感じ、診察に向かいます。
これまで、何とか30年あまり医師として、心身もボロボロになりながら精一杯、医師をやってきました。
大学病院でもクリニックでも患者さんの期待するものは変わらないと思います。ただ、30年の医師人生の中で強く思うのは、毎日、患者さんをしっかり診て受け止めることが、次の患者さんの治療に役立ち、人はつながっているのだなと思う。
著者:いしづかクリニック
院長 石塚 俊二