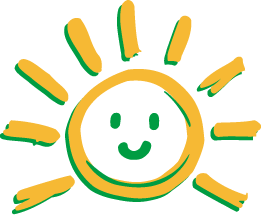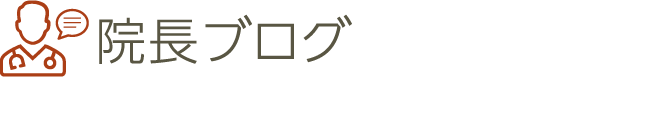
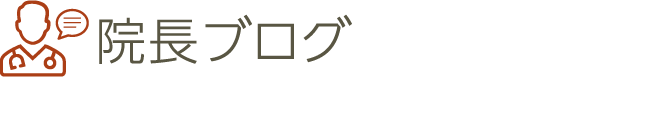
11 日常のありがたさ
誰でも日常生活は変化がなく退屈であると思うこともしばしばある。また、普段の生活では自分のおかれている環境や周りへの感謝を実感として感じることがなかなかないかもしれない。しかし、非日常から元にもどるとそれをしみじみ感じる。
病気に罹ることもまったく同じことだと思う。やはり健康な時はそのありがたさを感じずに仕事で無理をしたり忙しくしたりすることをいとわない生活をする。僕の場合はむしろその忙しさに酔いしれることがあり、ハードワークをすることが自分に充実感や満足感を与える“ワ-カ-ホリック”のようなところがありここまできた。
忙しくすることや長時間勤務で多くの仕事をこなすことが、医師としての当然の義務で自分の使命だと思いそれを誇りに感じていたところもあると思う。しかし、最近、少しその考え方に変化がでてきたことを自覚するようになりました。
そのような思いで生きると、“次にするべきことは何か、何をしなくてはならないか”と次に次にと前のことばかりを考え、今を振り返ることが少ないように思えます。つまり、今の日常が見えていないことがあるように思える。
病気に罹ると人は健康のありがたさをしみじみ感じる。“どうしてもう少し早く病院で検査しなかったんであろう”
“わかっていたのになぜ早く治療薬を飲まなかったんだろう”と誰もが病気に対する不安、後悔を感じる。
そのとき初めて健康であり日常生活を送っていたことを大切感じると思う。
人が癌にかかるとある心理的変化が起こるといわれている。癌ではないという“希望”から始まり、不安・困惑→疑念・否認→確実性→覚悟・受容と変化していく。この間は常に“日常と非日常”を意識している。
毎日、起きて、ご飯を食べて、家族と話し、仕事をして、お風呂に入って、寝る。
気に入らないこともあるだろうし声を荒げて喧嘩したり、また大きな声で笑ったり、悲しんだりしながら毎日を過ごす。
しかし、“当たり前にある日常のありがたさ”は、病気によって一瞬で崩れることがある。
僕は高校の時に親友の一人と一緒に医師になることを目指していました。彼とは自宅も近くでクラスも同じで毎日通学も一緒で3年間ずっと学生生活を共にしてきました。
その友人は5年間の浪人生活の後に晴れて国立医学部に入り麻酔科医となった。合格したときは本当にうれしかったことを思い出します。
私が医師として7年目で留学を控えていた時でした。彼は卒後2年の研修を終えた時に白血病に罹り突然に命を落としました。彼の無念や悲しみは想像を絶するものであり、初めて連絡が入った時は、私は呆然ととなり信じることができませんでした。“医学部に入るのに一番苦労して頑張ったのに” “卒後2年目でやっとこれから自分の専門を決めて臨床、研究に集中できるのに” “あんなに元気だったのに”とそのような思いが頭をかけめぐり、しばらくは気持ちの整理がつかなかったことがありました。それからは、20数年が経っています。
以後、仕事が前のめりになり、次に次にと前が見えなくなり医師としての判断に迷い挫けそうになった時にはいつも彼を思い出し、“僕は今、医師をやれているんだ” “彼の想いも入っているんだ” “それだけで十分だと”と日常を思い出し、感謝し自分を鼓舞するようにしてきました。
最近はその日常のありがたさを感じる時間が多くなってきたような気がします。その気持ちもやはり患者さんから教えられます。特に高齢者は命の大切さをより感じてわかっていると思う。
“腰や肩が痛い” “ふらふらする”といった毎日同じように聞こえる訴えでも、患者さんには昨日の日常の症状とは違うのであろう。だから、一日の中で調子が良いと感じる時間に幸せを感じ、生きる喜びと感謝を深く思っているのだろう。
この気持ちを考えながら診察すると患者さんの毎日の同じような訴えのなかの違いが見えてくることがある。それを見つけた時には患者さんとのやりとりもより素敵な会話となり楽しい時間が流れる。
 在宅診療でも日常のありがたさをより強く感じる。以前に肺癌の終末期の患者さんの往診をしていた。食事が減っていき、徐々に薄れていく意識の中での会話であったが、私が“今一番食べたい物”を聞いたときに“自宅近くにある愛蓮という中華屋さんの焼きそばが食べたい”と笑みを浮かべて言われ、“僕もそこはよく行きます。炒飯もおいしいですよね”と答えるとゆっくり頷いて笑顔を浮かべていたことを思い出した。やはり“日常はすばらしい” “日常はありがたい”とつくづく思う。
在宅診療でも日常のありがたさをより強く感じる。以前に肺癌の終末期の患者さんの往診をしていた。食事が減っていき、徐々に薄れていく意識の中での会話であったが、私が“今一番食べたい物”を聞いたときに“自宅近くにある愛蓮という中華屋さんの焼きそばが食べたい”と笑みを浮かべて言われ、“僕もそこはよく行きます。炒飯もおいしいですよね”と答えるとゆっくり頷いて笑顔を浮かべていたことを思い出した。やはり“日常はすばらしい” “日常はありがたい”とつくづく思う。
著者:いしづかクリニック
院長 石塚 俊二