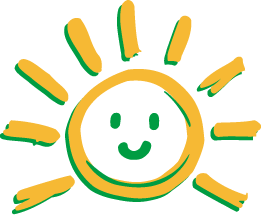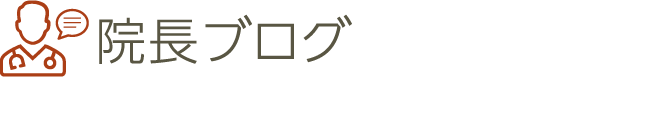
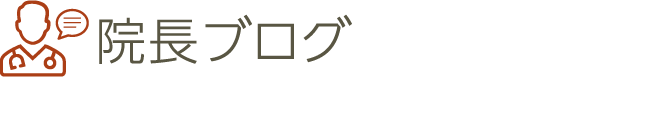
18 在宅診療後のアフタ-
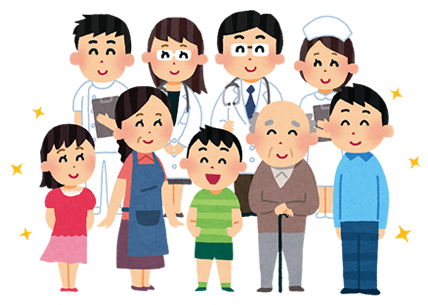
2022年が始まりました。当院も昨年は、一般外来、膠原病・専門外来、在宅診療に加え、感染症外来、コロナワクチン接種、オンライン診療など多岐にわたる診療体制で今年もしばらくはこの体制を継続している。
そんな中で先日、昨年、訪問診療にて自宅で天寿を迎えられた患者さんの奥様がふと外来診察に来られた。
夫が亡くなられてからこの1年間ずっと沈んだ気持ちを立て直すことができず、抑うつ状態や不眠に悩み内科や心療内科などたくさんの病院に通い、それでも症状が改善されず私に相談のために来院された。
訪問診療では患者さんはもちろん家族との関係は非常に重要で、患者さんとの診察後は必ず家族との話し合いの時間を作るようにしている。
在宅加療中は家族に先の見えない不安があります。患者さんの痛みや苦しみを目の当たりにしてとても不安で悩みもあります。そんな家族には寄り添い、疲れていないか、悩んでいないかなどを注意深く見守り、一人で抱え込まないようにと声をかけるようにしている。
介護疲れの時はショートステイやレスパイト入院などの利用も勧め常にその家族全体の考えを見るようにしています。しかし、このような診療は患者さんが亡くなられると必然的に家族のその後の生活の変化や精神面まで深く考えることはなくなってしまうようになっていました。
この奥さんが来院し夫のいない寂しさを1年以上持ち続け強く訴え時には、僕はこのようなことを全く気付かなかったことの後悔と医師としての傲慢さを覚えずにいられませんでした。
在宅医療は亡くなられた時が終了となるけど、ご主人が亡くなっても奥さんの人生はそこから先もあるわけでその配慮に全く欠けていたことを痛感した。
大切な人を失った家族の悲しみは、たいていの場合なかなかすぐに拭いきれるものではない。
現実の感覚がなくなったように思えたり、悲しんだり、疲労感などで体の不調もでてくる。
大切な人が永遠にいなくなったことで、家族の生活も変化するでしょう。悲しんだり、疲労感を覚えながら現実の生活の変化に対応していかなくていけない。

大切な人の喪失体験により、さまざまな心理的・身体的症状を含む情動的(感情的)反応を“グリーフ”と呼ぶ。
大きな専門病院においては、癌の治療でがん患者さんや家族の心の支援を専門にする医師(精神腫瘍科、精神神経科、心療内科など)や緩和ケア医、心理士などが存在し治療に当たることもあります。
グリーフは人によって程度はさまざまですが、こうした悲しみの気持ちは一般的に月や年単位で続くといわれます。
この奥さんにとって、ご主人の存在を無理やり忘れようとしても悲しみは癒されないと思います。むしろ、喪失や悲しみに遭遇するたびに、「忘れよう」「考えないようにしよう」といって、回避を重ねる道を選んでしまうと、逆に現実に向き合うことが難しくなってしまうこともあります。
喪失による苦痛を乗り越え、充実した生活を取り戻したという方のお話を聞くと、「大切なひとが自分のなかで存在し続ける、と考えるように心がけた」ということをよくおっしゃいます。
大切なひととの関係性を、目に見える「身体的な存在」から、目に見えない「心の絆」として自分のなかに刻み込まれているようです。だから、実際にひとりでもあまり寂しさを感じないそうです。また、そのような気持ちを少しずつ持つようになると、思い出すとつらくなるからと、大切なひととの思い出をいつまでも封印し続けたりしなくてもよいことがわかります。
また、グリーフ(悲嘆)に対処することによって、人間の命には限りがあるということに改めて気づき、その現実を受け入れたうえで、最も大切な人々との関わりや、大切な計画を優先し、残された時間を有意義に活用しようと考えることもある。
こうして、喪失や悲しみの気持ちから、新たな生活、人生に歩み出していけるようになるのではないかと思う。
その窓口に在宅医師が係わることができるのではないか、いや係わらなくてはいけないのではないかと思う。
病院ではグリーフに対する専門の医師がいるけど、在宅医療では家族にとっての医師は在宅医のみである。在宅終了後であっても、まずは、医師が家族の気持ちと静かに向き合ってみる。それが難しければ、ご自分の心のうちを親しい人に話してみてくださいなどのアドバイスはできるのではないかと思う。
残された親しい人同士の語らいの場や、同じ思いを抱きながら過ごした方からのメッセージが参考になることもあります。家族は喪失による痛みや苦しみと対峙することによって、今まで気づかなかったご自身の感情や願いがみえてくることがよくあるのではないか。また、それが家族自身の感情の変化に気づいたり、見つめ直したりするきっかけにもなり、これからの生活での苦しみや悩みに対しても方向性を見失わないで、落ち着いて対処することができるかもしれないと思う。
在宅医は患者さの看取り後も在宅医療は続くことを考える必要があると思う。
著者:いしづかクリニック
院長 石塚 俊二