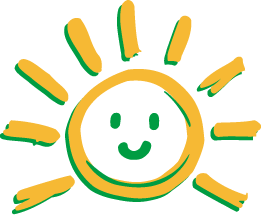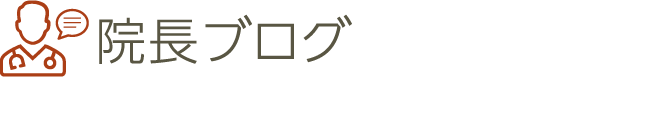
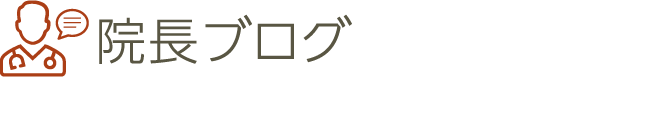
38 死と向き合うとは
医師という職業は多くの患者さんの死について直面する。
これまで私も多くの受け持ち患者さんの看取りをさせていただいた。
大学病院の専門医で働いていた時の膠原病や腎臓病の患者さん、地方の老人施設で入所していた時の患者さん、救急病院で搬送されすぐに命を落とされた患者さん、そして現在のクリニックで外来や在宅で受け持っていた患者さんなど小さなお子さんから老人まで、また人工呼吸器やたくさんの点滴を繋ぎながら治療した患者さんや全く何の医学的処置や治療を施さないで自然のまま天寿を全うされた患者さんなどその最期を立ち会った患者さんは数百名を超えると思う。

先日も数十年間の長く在宅医として診察に携わっていた患者さんの最後に立ち会った。
患者さんとの付き合う期間が長ければそれだけその死は自分の心に重く突き刺されるのだが、このような医師としての経験の中で、自分なりの死生観も年齢を重ねるとともに少しずつ変化していることに気づくようになった。
若い時は、とにかく患者さんに一日でも長く生きてほしい。そしてそれを患者さんが希望するなら人工呼吸器、血液透析、中心静脈栄養、人工心肺など循環、呼吸、代謝、栄養などどんな方法を使っても長く生きてもらうことが医師の使命だし、それが患者さんの望むことだと信じて医療を行ってきた。
つまり治療の限界に達するまで行うことが医療の最善、最適だと思っていた。しかし、私自身年を重ね、在宅医として約20年間患者さんの最後に立ち会い死とは年齢だけ、生きた時間だけで推し量れないということを体験し実感することが多くなってきた。
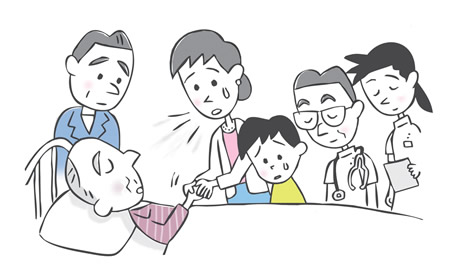 死ぬのは恐ろしい。なぜ恐ろしいのかうまく説明できないがとにかく恐ろしい。恐ろしいことは考えにくい。
死ぬのは恐ろしい。なぜ恐ろしいのかうまく説明できないがとにかく恐ろしい。恐ろしいことは考えにくい。
また、死ぬということは考えにくい、手がかりがない。手がかりがないのはやっぱり怖い。こんな感覚で人は捉えがちである。けれども、死ぬということが考えにくく畏敬を抱くほんとうの理由は、死ぬということは、ものを考える“このわたし”が存在しなくなることだからであると思う。では存在するとはどういうことか。
例えば、庭先にリンゴの木があるとする。リンゴの木は存在しているし、その証拠に目に見えるし、触れることもできる。仮にリンゴの木が枯れてしまうとリンゴの木は存在しなくなる。どんなものでも、存在したり存在しなかったりする。つまり存在していたのに存在しなくなったり、存在していなかったのに存在するようになったりする。リンゴの木は存在する。そう言うことに意味があるのは少なくとも誰かがそのことを確認できるからだ。誰もリンゴの木を見ないなら、そして触れないならリンゴの木の存在を確かめようがない。そのリンゴの木が存在するとかしないとかいうことに意味がない。
あるものが存在するとは、そのものが経験できるということで、言い換えると“存在するものは経験できる”ということである。では存在するものが存在しなくなったらどうなるか。経験されるものが経験されなくなる。このことも経験である。そこで次のように言える。
“存在するものが存在しなくなることは経験できる”ということが、死生観につながるのではないかと思う。医師が死生観を話すとは不謹慎と思われ、死に関して考えるのは縁起でもない、後ろ向きな考えではないかと思われる方もいるかもしれない。しかし、死生観は死ぬことのみを考えるのではなく生と死の両方を考えることを意味していると思う。
患者さんを診察する。その患者さんを見る、触れる。その患者さんが生きていることを経験する。その人が亡くなれば、見ることも触れることもできない。しかし、人は生き物として生きてきた。そのことを経験できる。人は必ず死を迎えます。そしてすべての人が人生を生きぬき、それを多くの人が見ていてその人に触れ人生を全うしていきます。最後になくなったことも、その人が存在し、生きぬいたからこそ亡くなり周囲の人もそれを経験していくことができるのです。
宗教によっても死生観はそれぞれです。例えば、仏教における死生観の一つに輪廻転生があります。これはいまある生命が失われた後、魂が生まれ変わっていくことを意味しています。すなわち、自分自身の肉体が亡くなった後も、魂だけは生き続け、別の肉体に生まれ変わるということです。この魂こそがその人が存在していたという経験ということになるのではと思います。死を迎え入れる心の準備ができたら、残された自分の人生を全うしようと考える人も多いです。
これは“生”について考えるとういことでもあり、後悔のない人生を全うするためにも重要なことだと思います。
ただ、死は存在していたことの証明でもあると考えると、そのまま自然に受け止められるようになるのでは思う。
人の一生も諸行無常のようである。
令和5年10月:いしづかクリニック
院長 石塚 俊二