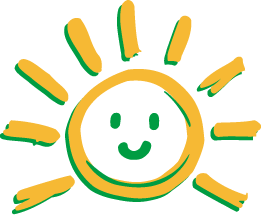63 伝える難しさ
 人に自分の考えや気持ちを正確に相手がわかるように伝えるのは本当に難しいと思う時があります。
人に自分の考えや気持ちを正確に相手がわかるように伝えるのは本当に難しいと思う時があります。
クリニック内で例えると、医師である私、看護師さん、受付さん、柔道整復師さんなど業務も多種にわたり、また、パートさんや常勤さんなど勤務の違いもありそれぞれの性格も加味すると、同じ方針を伝えるのでも実に難解であると感じるときがある。
時には、発言することで違う意味に理解される場合や、それから別の問題に波及する時もあります。皆さんは会社や友達の関係でどのように自分の思いを伝えていますか。
私の場合、仕事での連絡や確認事項について伝えないといけないことがあるときは注意していることがあります。
それは、まず“その話の本質を理解してもらう”ことを意識しています。
“なぜその案件が重要なのか、それを伝えなければどのような結果になるのか”その仕事を遂行することによってどのような影響がでるかということです。
例えば、訪問診療している患者さんが入院の希望があるときは、何度も連絡が行き返されます。入院先の病院へ連絡し、紹介状のFAX確認、家族への病院の決定連絡、搬送の方法や時間、訪問看護への連絡、薬局への入院報告など1回の入院でも複数回の連絡が必要になり、これが一連したものでどこかが止まれば完結することができなくなります。
もちろん、FAX、メール、電話だけでなく、ショートメール、LINEなどのSNSも駆使しながら行いますが、それでも対外的な連絡が一気に増えます。
時に、当院で連絡事項がひとつでも止まると、最終的に患者さんに不備、不利益が生じてしまいます。
個々の1回の連絡では全体の流れや仕事内容の重要性を把握することができないので、その連絡が滞るときは、なぜ、その1回の連絡の滞りがどのように全体に影響するか、仕事のつながりをすべて説明し、連絡の意義や本質を説明するようにしています。その仕事の流れや意義を理解することで、自宅にいる患者さんの姿が想像できるように心がけています。
常に僕自身が意識しているのは、“フィードバック”を行うということです。
フィードバックもいろいろな方法があります。
フィードバックは行う側の視点で定義付けると、相手がどういう状態なのか、自分にどう見えているのかを自分の言葉で伝えて、相手の行動を改善してもらうことです。
フィードバックは耳の痛いことを相手に通知し、相手の行動改善を狙うことを目的とした「ネガティブフィードバック」と、相手の良いところ・強みとなる行動を相手に通知し、さらに望ましい行動を促進・強化することを目的とした「ポジティブフィードバック」の2種類があるといいます。
一般的に日本人はネガティブなこと言われてしまうとひどく落ち込んでしまう人が多いとされています。では、どう伝えたらよいのでしょうか。
 ネガティブなフィードバックを1つ行う場合に対してポジティブな声かけを3つ行うような比率で接すると受ける側の「貶されているような気持ち」が軽減されるという話もあります。
ネガティブなフィードバックを1つ行う場合に対してポジティブな声かけを3つ行うような比率で接すると受ける側の「貶されているような気持ち」が軽減されるという話もあります。
このフィードバックで最も大切なことは『信頼感の確保』です。
相手に話す際には相手の心理的安全や信頼感の確保がないと仕事の本質や意義について説明してもまったくお互いの理解は得られることはありません。
つまり、フィードバックを受け入れる準備が出来ていない時に行ってしまうと、聞き入れて貰えなくなったり、人間関係が崩れてしまうといいます。
このようなフィードバックのタイミングは上司と部下のような関係に留まらず、親子関係などでも重要視されます。
言い換えれば、信頼感の確保というのは、相手の成長を願い、相手の人間性をリスペクトする態度が大切ということになります。実際、コミュニケーションの際、言葉は全体情報の7%に過ぎないといいます。
声のトーン・高低・強弱が40%程、表情などが50%程を担っているとされています。
アメリカのとあるリーダー研修では演技のトレーニングが組み込まれている所もあります。
つまり、表情や声のトーンを工夫し、この人は自分の成長を願ってくれている、愛情で言っていると表現する事も重要です。
話が飛びましたが、本当に大切なことは相手のことを想いながら、自分の気持ちを理解してもらう努力を自分がし続けないといけないということですね。
令和7年11月:いしづかクリニック
院長 石塚 俊二